こんにちわたいらです。
目下のリモートワークの普及に伴って耳にすることが増えてきたこの「ジョブ型雇用」というワード。一般的には、終身雇用や年功序列といったNIPPONの伝統的雇用形態が崩壊する中で「メンバーシップ型雇用」から「ジョブ型雇用」へと変化せざるを得ないよね、という言い方がなされているわけです。
どこまでその変化に対してドラスティックに、スピード感を持って対応できるかが企業の生産性を左右します。
web制作やってんだけど、先月異動してきた上司がずっと経理で話通じないんだよね
好きで営業やってたのに急に内勤の広報部署回されてモチベーションだだ下がり・・
あると思います。というよりも、終身雇用やメンバーシップ型雇用の必然的な副作用じゃないでしょうか。
私が過去にどっぷり浸かっていたホテルやレストラン等の対面接客業では「ジェネラリスト」「スペシャリスト」といった表現がされることが多かったのですが、この潮流がどのように作用し、企業と従業員はどのように受け止めて行動すべきかについてちょっと考えてみました。ちょっとだけ。
というのも、サービス業を一定年数やっていると
- 現場を回し、お客様にご満足いただくことに全力を注ぎたい人
- 数値上の責任を負いながら組織上のステップアップを図りたい人
の2通りに別れがちなんです。私個人的には2.が普通だろうと思っていましたが、びっくりするくらい1.の割合も多いことにある時気付きました。単純に「数字なんて見たくない、わかんない」って人も一定数います。
結論としては、
サービスと数字作りのスペシャリスト同士が仲良く喧嘩して、その上にバランサー(経営層)がいる状況が最も組織上健康的なのではないかと考えています。
言い方を変えると、「サービス」というジョブと「数字作り」というジョブの二本立てで各スタッフがキャリア形成を選択できるのが理想ってことです。
ジョブ型雇用とは

企業側が必要とする職務や求める技能を限定したうえで、「仕事に人を割り当てる」採用を行う。
コトバンクより引用
よくアルバイトの募集で「ホールスタッフ募集」とか「テレフォンオペレーター募集」とかあるじゃないですか。要はアレを正社員採用だろうが新卒採用だろうがやっていきますよー、というのが分かりやすいかな、と。もちろん「プログラミング」や「webマーケター」といったより高い専門性を求められがちなわけですが。
当然のことながら企業側が求めるのは即戦力。中途採用であれば既に一定のスキルを持ち合わせていることが条件になるでしょうし、新卒採用であれば「この道で生きて行く」という覚悟と予備知識が必要になってくるでしょう。
実際に日立や資生堂もジョブ型人事制度への移行を打ち出しています。経団連も含めてえらいひと達がいろんなとこでいろんなこと言ってるんですが、私なりに要約しますと、
- 適材適所に要員配置を行うことで生産性を高めたい
- 労働時間ではなく成果にフォーカスすることで正当に評価、給与に反映させたい
- 高度な専門性を持った人材を育成することで外注費用を抑えたい
こういったところに目的があるんではないか、と。
要は企業も限られた人的資本の中でのパフォーマンス最大化を迫られてるってわけ
リモートワークについては限定的ですが、対面接客業に関しても上記のような目的を持っていることに違いないので「企業生産性」「個人キャリア形成」2つの観点から今後どういった潮流になっていくのか、予測検討して参りたいと思います。
私の前職(リゾート施設の運営会社)
わかりやすくするために、ホテル事業に限定して紹介します。

職種について
ザッと思いつくだけでも下記のセクションがありました。業務内容についてはこんなにきれいサッパリ切り分けられるものでもないので参考程度に。
| フロント | 宿泊予約管理、チェックイン/アウト、施設販促、付帯業務 |
| レストラン | 喫食予約管理、料理提供、付帯業務 |
| 厨房 | 食材管理、調理、付帯業務 |
| 施設管理 | 施設内インフラ整備、特殊清掃、付帯業務 |
| 施設清掃 | 客室清掃、共有部清掃 |
んで、もちろん各セクションには管理職と一般職(プレイヤー)がいるわけです。規模によってはプレイングマネージャーみたいな人も散見されましたが。
厨房と施設管理に関しては専門職の色合いが濃いので別のくくり感はありました。加えて施設清掃については外注に出してる施設がほとんどでした。ですがレストラン⇔フロント間に関しては2週間前とかの内示でペロっと異動が命じられることがあるわけです。これは組織構成関係ないですがもちろん施設間異動もあって、九州から北海道へドラコンなんでことも。
で、こういったセクション管理をする上で私が感じた問題点をちょっと挙げてみます。
問題点1:異動によるモチベーション低下
セクション間の要員バランスを調整するために、「フロント⇔レストラン」の施設内異動なんてしょっちゅうあるんですよ。「絶対やだー!!」なんつって泣き出す輩なんてザラでした。
理由は様々なんですが、生活パターンが変わることへの抵抗や、残業のボリュームが変わること、体力面スキル面の不安等が多かったように思います。引越を伴う場合はさらに「家族から離れちゃうよ~」とか「知らない土地行くの不安だよ~」とか始まる。一番くだらなかったのが「フロントのスカートが無理」(笑)
は?甘えてんじゃないわよ。
いやまぁそうなんだけど。フロントとレストランって恐らく想像以上に業務内容が違うのは事実です。フロントはたぶん一般的なイメージに近いと思うんですけど、レストランは相当体力的にハードです。路面の居酒屋さんやカフェとは実際訳が違います。一方でフロントはPC作業も多いので、あまりにレストランが長いとPCアレルギーが発症する場合もあります。
お食事を楽しみにされてるお客様はたくさんいるので、ホテル滞在中の最もご機嫌な2時間を接遇できる歓びもひとしおでして。ゴリゴリのサービスマン思考の人はレストラン勤務を好む傾向があります。
問題点2:セクショナリズム

ホテルマンのサービスついて、皆さんもこんな風に感じたことがあると思います。
- この人すごく物腰が柔らかくて心地良い接客をしてくれるなぁ
- テキパキしていて見ていて気持ちが良いなぁ
- ホテルマンらしい、温かくてスマートな言葉遣いができる人だなぁ
そんな折申し上げにくいんですが、ホテルマンの一般職ルーティンワークの専門性はそんなに高くないんです。慣れと意識の問題だけで。フロントにおけるレベニューマネジメント(客室の価格調整、プラン作成)だとか、レストランにおけるワインや料理に関する知識とかって話になりますが、意欲的に取り組めば1年で十分身に付きます。その余裕が生まれるまでの期間は人それぞれですが。
で、冒頭申し上げた通り、キャリアを積むに従って「サービスバカ」と「数字バカ」のいずれかに傾倒していく人が非常に多いです。
ホテルで働こうって人はサービスがしたくて入社する人が多そうだけど。
そうなんだけどね、一定のポジションになると会社からは数字を求められるから。
数字を基準としない管理能力ほど役に立たないものはないわけで。かと言って中長期で見た時最強の販促ツールとなるサービス水準をおざなりにするとしっぺ返しを食らうのは目に見えているわけで。企業としてはそこらへんのバランスを取ることがとっても重要で大変なんです。
最大のデメリットとしては、各セクション長が施設数値ではなく自セクションのサービスや数値を優先してしまうこと。これをこじらせて年中犬猿の仲になってるケースも散見されました。そういった施設はもれなくESもCSも低下の一途を辿ります。
メリット:スキルをアピールし易い
ここまでで終わってしまうと悪口ばっかりみたいになるんで、スタッフ側のメリットも挙げておきますね(笑)
- 特定セクションでのスキルが突き抜けていれば開発やイベントの際に社内で重宝される
- 若干軸をズラした転職の際に武器になることがある
1.は本人にとって間違いなく貴重な体験を積み、ステップアップへの近道になりますし、2.については実際数件目にしてほっこりしました。フロント部門で磨いた接客スキルを評価されて司書になった方、フレンチレストランで磨いたサービススキルをアピールしてCAに転職した方なんかもいましたね。
ホテルで働いてましたー。いろいろやってましたー。
に比べれば専門性を訴求する材料にはなるかな、と思います。
星野リゾートの場合

当項目については実際に内側を覗いたわけではないので個人の憶測を含んでいることを予めご了承ください。
職種について
かの有名な星野リゾートでは「フロント」「レストラン」「客室清掃」に至るまでを全スタッフが従事するマルチタスク方式を導入しています。
お客様の滞在の流れに沿って、レストランサービスからチェックアウト業務、清掃まで一人のスタッフが担当します。
東洋経済オンライン 星野代表コメントより抜粋
これはチームの生産性を上げるうえで実に理にかなっています。なぜならフロント、レストラン、客室清掃はそれぞれピークタイムが違うから。
| フロント | 9:00~11:00(チェックアウト)、15:00~17:00(イン) |
| レストラン | 7:00~10:00(朝食)、18:00~20:00(夕食) |
| 客室清掃 | 11:00~15:00 |
改めて見るとほんとキレイにズレてるんですよね。とは言え、前項のセクション分けと比べると以下のような問題が想像されます。
問題点1:スタッフの消耗がキツいのでは?
朝食サービスを終えたらフロントでチェックアウト業務をこなし、客室清掃をして終業、といった流れが想像されます。お客様の視界に入る時間や忙しい時間が長くなるようだとそれだけスタッフの消耗も激しいのではないかな、という印象はあります。
また、職域が広ければ当然覚えなければならないこともたくさんあります。網羅的に習得しなければならないプレッシャーや、自分がやりたいこととそうでないことがハッキリしてしまってストレスにつながってしまうのでは、という感じがします。
問題点2:ガバナンスが効きにくいのでは?
セクションが無い(少ない)ということは役職者、管理職の数も少ないことが予想されます。
フラットな組織文化では、肩書きではなく何を言っているかが問われます。これまで情報量の差やマネジャーの権限など肩書きだけで自分のステイタスを維持していた人は、それを維持できなくなる。
東洋経済オンライン 星野代表コメントより抜粋
これって実力主義に見えるかもしれませんが、ややもするとただ声の大きいだけ人がチームワークを乱したり、特定のターゲットにストレスを与えたりすることになるんじゃないでしょうか。
きちんとやるべきことやって、周囲からの信頼も厚くて、CSや数値作りについて有効な施策をロジカルにプレゼンできる人が評価される風土ができているなら良いのですけど。いやぁ、怪しい(笑)
メリット:圧倒的生産性

項目見て「え!?」ってなったそこの貴方、正解です。私の前職におけるメリットではスタッフ側の目線なのにしれっと企業側のメリット書いてやったぜ。
実際に前職の現場においてもジョブローテーションをしながら脱セクショナリズムを図ったこともありました。ただ一度根付いた文化はなかなか変えるのはしんどいんです。
こと人件費あたりの生産性については間違いなく星野リゾート側に軍配が上がります。だってスタッフにとってのアイドルタイムが無いんですから。ずーっと忙しい。
あくまでネット調べですが、星野リゾートは業界内で特段賃金水準が高いわけではありません。離職率も高いですし。ただしブランド力から来るとんでもない採用力でそれをカバーしてるものと思われます。
正解モデルの個人的見解
「企業生産性」の観点から
今後ますます加速する要員不足を考慮すると、既述の通りセクションの無い星野リゾート型組織の優位性が増すものと考えています。セクショナリズムから来る摩擦も将来的には無くすことができますし。
ただし、これからそういった組織を目指す場合は、少なからずスタッフからのアレルギー反応が起こることは想定しておかなければなりません。
- 組織改編を受け入れるスタッフへの還元方法(給与が望ましい)
- 教育・評価制度、マニュアルの整備
- 以下に記述する「個人キャリア形成」へのフォロー、システム作り
マニュアル整備については対面接客業を対象とした記事がありますのでよろしければご参照ください。
「個人キャリア形成」の観点から
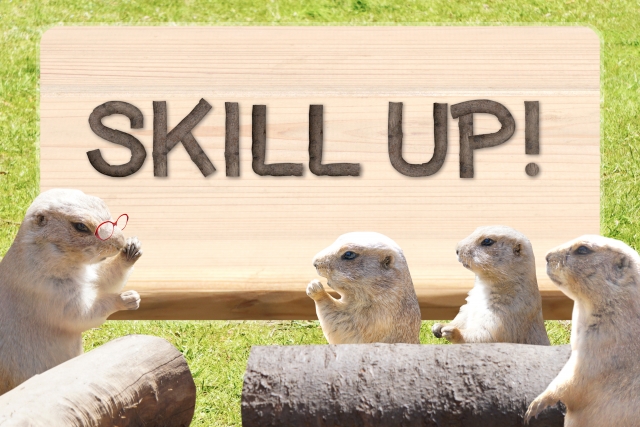
考えてみれば当たり前なんですが現場で働くスタッフの人数分、経営層の椅子の数が用意されているわけではありません。ということは、
あたし数字の管理とかやりたくないの。現場のサービスでお客様の笑顔を見てたいの。
という人にも企業側にとって十分価値があるということです。しかしながら、給与等の条件面では頭打ちになるでしょうし、レストランだけフロントだけといった職域の限定を自分でコントロールすることは難しいでしょう。
「現場におけるサービス業務全般」を自身のジョブであると言い切る決意表明が必要です。
一方で現場で着実にステップアップしてゆくゆくは経営全般や開発、マーケティングといった企業の中核業務を担いたいのであれば、
まずは現場の数字を改善するための施策を立てて実行する能力を育てなければなりません。
私個人としてはこの2種類のキャリアコースを明確に分けることが望ましいと考えています。場合によっては後者のコースに必要な社内資格等を設けることも有効でしょう。
まとめ
今回ホテルを題材にしましたが、今後サービス業全体において省人化や自動化といった大きな構造変化が予想されます。
- サービスをジョブと呼ぶだけの希少性、専門性、ユーティリティがあるか
- サービスの生産性を向上させるための分析能力や改善ノウハウがあるか
企業側も、スタッフ側もこういったところを念頭におきながら組織作りやキャリアマップを共有することが肝要ではないでしょうか。














