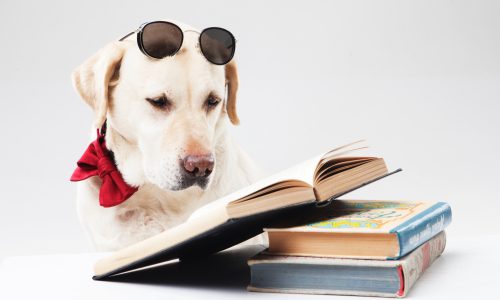2020年5月23日、恋愛バラエティー番組「テラスハウス」に出演中だった木村花さん(享年22)が亡くなったことが所属するプロレス団体スターダストから発表されました。
公にはなっていないものの、番組内でのご本人の言動に対してネット上で過激な誹謗中傷が展開され、それが彼女を追い詰めたという見方が強くなっています。
私自身ほぼ番組を見たことがありませんし、このニュースを知るまで彼女のことを存じ上げませんでしたが、この件に関して様々な著明人、インフルエンサーの方々が意見を述べられています。
少々ドライな内容になってしまうかもしれませんが、それらを俯瞰的に整理し、再発防止のためにはどういった対策や世間一般の共通認識が有効なのかとりまとめました。
尚、正確には知り得ない上にご遺族やファンの方の心中を尊重するため、当該案件の経緯については以降触れません。
法的な整備、罰則強化の壁
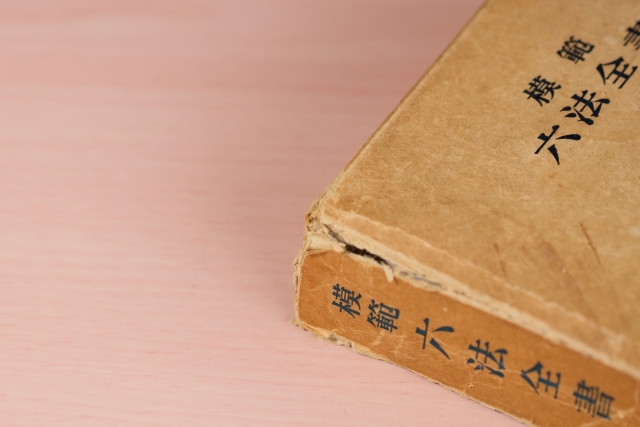
法整備は当然挙げられる選択肢であり、実際5月25日には菅官房長官発信者の情報開示についてプロバイダー責任制限法に基づいた議論を開始している旨を述べています。
ただし、具体的な立案には様々な障壁があります。
現法制での対応
ブログをはじめとしたインフルエンサーとして知られるイケハヤさんは自身のYouTube内で次のように述べています。(以下要約)
既存のルールでは個人の特定と弁護士費用で60万円~の費用がかかる上、被害者側が支払い能力を持っていないケースが多く訴訟のメリットがあまりにも乏しい
https://www.youtube.com/watch?v=z-o96rAL21Y
他の著名人も述べている通り、アンチに対しては「見ない」「スルー」「ブロック」といった対処しか事実上できないようです。
しかしながら住所を特定しての嫌がらせ行為等、見逃せない危害を加えられるケースも多々発生しているのが現実です。ご家族等が対象となり得ることも加味するとご本人のおっしゃっている通り「有名税」で済まされるものではありません。
「表現の自由」とのバランス
法改正において最も大きな障壁となる「表現の自由」とのバランスについて、橋下徹さんは次のように説明されています。(以下要約)
誹謗中傷は正面からの批判を含むため、短絡的に禁止することは民主主義の根底を揺るがしかねない。したがって現状はSNS運用会社に事後的な裁量を委ねるしかない。
https://www.youtube.com/watch?v=_gyGE6U9JXM
現実として5月24日に「#さよなら安倍総理」がツイッター上でトレンド入りしています。
「さよなら」が辞任を求める民衆の声と捉えるならばある程度健全と言えるかもしれません。が、安倍総理ではなくあなたの個人名だったら?何の発信もしていない未成年者だったら?
「死ね」「ウザい」といった直接的表現だけでなく、具体的線引きをどのように引くのかがいかに困難でデリケートかご想像いただけるのではないでしょうか。
匿名性の問題

「実名公表した上での発言なら問題ないのでは?」という意見も見受けられます。これは発信に責任を持つこと、そして誹謗中傷の抑制に対しては大きな効果を持つでしょう。
しかしながら既に文化として根付いている、匿名であるが故の気軽な情報発信や意見交換にも制限を設けることになります。インターネット上の掲示板や知恵袋で実名が義務付けられることを果たして世間が許容するでしょうか。
それでも訴訟する!!
メンタリストDaiGoさんが以下のようなツイートをしていらっしゃいます。

イケハヤさんが「アンチへの訴訟はコスト、手間の面でメリットがない」とおっしゃっていたのは先述の通りですが、最後の一文から察するにDaiGoさんは百も承知でチャレンジするということでしょう。
どういった結果になるのか、個人的にも非常に興味深いです。アンチが一定のダメージを負うことが広く浸透すればSNSのネガティブな部分が改善されるかもしれません。
「自殺=悪いこと」という認識の拡大

ご遺族にとっては残酷かと思いますが、未然防止のためには必要な考え方だと思います。今回の件に関するコメントかどうかの裏が取れなかったのですが、松本人志さんも以前同様の主旨の発言をされていたようです。
みんなが味方してくれると思ってる。大人達が「自殺は悪」であると声を大にして教えてやんなきゃいけない。
マスメディアの在り方
ひろゆきさんが上記のツイートをしたのが以下記事からの引用RTです。
制作側がわざわざ蒸し返している件、リアリティーショー出身で去年まで38人が自ら命を絶っている件。目から鱗でした。
つい最近まで一般人だった若者が突然マスメディアによってパーソナリティを晒されることになるのは大きなリスクを伴います。それらを十分に本人達に認識させ、批判が起こった場合に心身をケアするスタンスがないのであればこういった番組を制作する資格はないと考えます。
まとめ
当記事にあるようなインターネットを媒介とした誹謗中傷は黎明期からずっと付きまとっている問題です。課題解決の難しさに加えてインターネットの変容に法整備が追いつかないというのが実情なように思われます。ですので正直なところこの機会にネットでの誹謗中傷に対しクリティカルな法案が立案されるのか、私個人としては懐疑的です。
法律ではなく、インターネットとどう向き合うべきなのか、というのをまずは「教育」として落とし込むことを優先すべきではないか、とちょっとだけ持論として提案して筆を置かせて頂きます。