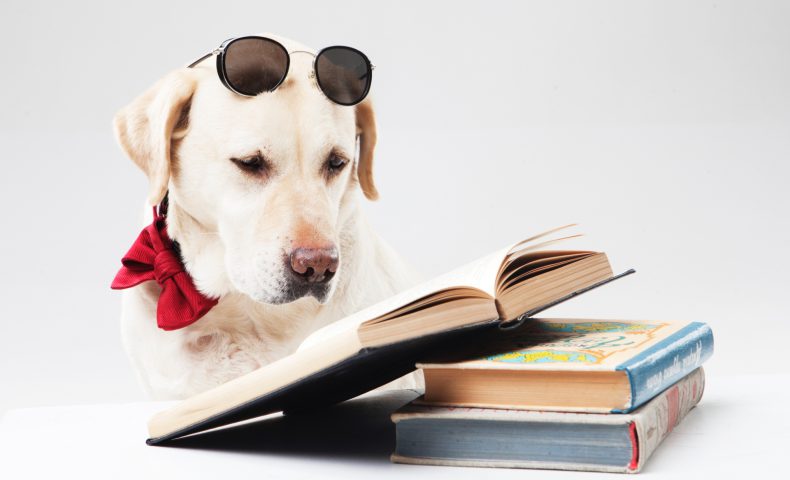上司からマニュアル作るように指示されたんだけど・・・
せっかく作るからにはちゃんと使えるものにしたいよね
- 過去に作成されたものはあるけれど、更新もされてないしそもそも誰も使ってない
- いろんな業務マニュアルが散らかっていて内容、仕様に一貫性がない
- 参考にしていたけど先輩達の言ってることがまるで違う
様々な現場を見てきましたが、上記のようなマニュアルの作成・運用における失敗事例がたくさんあります。
ただ作るのは簡単ですが、実際に教育や業務の平準化を目指すツールとして根付かせるためには相応の覚悟とコツが必要になってきます。
もちろん世の中には様々な業種や職種があり、マニュアルのあるべき姿も異なります。
しかしながら「マニュアルに実用性を持たせる」という目標においては共通した5つのポイントがあるため、当記事ではそれらを取りまとめました。

出来る限り包括的な1つのデータにまとめること
極論1つの法人、団体のマニュアルを1つのデータにまとめることが理想です。
- 営業部隊と制作・運営部隊の折り合いが付かずにケンカばっかりしてる
- 一般管理部門が勝手に自分たちの職域を狭くしてる
- 本部と現場が責任を擦り付け合ってる
これらは経営方針や組織、分掌構造が十分にブレイクダウンできていないことに起因します。
マニュアル上で明文化し、詳細を各部門各事業に分岐させることが肝要です。
同じ会社で働く仲間なら同じ方向を向いて仕事したいもんなー
新人教育に主眼を置いたツールであること
いくら立派なマニュアルが出来たところで、出番そのものがなければ形骸化は免れません。
異動や採用時の研修資料として機能するものであれば、教える側は再確認することができ、教わる側にとっての生命線となります。
この際、教わる側がメモを取らなくても良い水準のマニュアルを作成できるかが非常に大きなポイントとなってきます。
このメモこそ業務平準化の妨げとなり、「先輩によって言ってることが違う」という教育あるあるの最大の要因であると認識してください。
メモの要らないマニュアル作成が企業側の責任ってわけね
既存スタッフへの落とし込みと定期的なリバイスを怠らないこと
「マニュアル=新人教育ツール」であるべきなのは先述の通りですが、とは言え既存スタッフにそれらが周知されていなければ「意識高い系新人」として揶揄されかねません。
完成したマニュアルは確定事項として既存スタッフに対してトップダウンする必要があるのです。
「みんなで作ったマニュアル」という発信が理想的だよね
また、市場の変化やオペレーション改善に伴ったリバイス(更新作業)も担当を決めた上で発生ベース又は定期的に行う必要があります。
定量的な人事評価を見据えた作り込みを行うこと
顧客ファーストなスタッフもいれば業務効率を最優先させるスタッフもいるでしょう。
どちらも必要な人材であることには違いないのですが、偏り過ぎていてはスタッフ間の摩擦や生産性低減を招きかねません。最低限求められる業務の質、スピードは定量的に可視化すべきです。
「マニュアル通り」をベースに個性や付加価値、能力を評価するのです。
ここに注力することで、
- 決められた時間内に成果を挙げられるスタッフ
- 残業時間とその対価を自身への評価として受け入れるスタッフ
どちらが優秀であるかを公平かつオープンに評価することが可能となり、同時にスキルや生産性の底上げを図ることができます。
100点満点のマニュアルを目指さないこと
質の高いマニュアルを作るのはかなり手間がかかるのね・・
ここまで読んでいただいた方にはお分かりいただけたかと思いますが、企業にとって本当の財産になるマニュアル作成は一筋縄ではいきません。
仮に飲食店を例にとってみましょう。
- 朝食と夕食を3店舗3業態で提供し、婚礼やラウンジも運営しているホテルレストラン
- 終日単一業態のファストフード店やカフェ
1.は2.の10倍以上のボリュームになることは想像に容易いでしょう。
私個人の経験で言いますと、2.の業態はPowerPoint資料20ページ程度で1日あれば作成可能です。(詳しくはこちらをご参照ください)
1.の場合はExcelやWord資料100~200ページ、2カ月程度を作成期間として見繕っておかなければなりません。そう、大変なんです・・・

飲食店に限らず、セクションやポジションが多岐にわたるほど必要な手間は膨れ上がっていきます。
ただし、良く考えていただきたいのは、そういった規模や業種であるほど膨大な教育コストが採用や異動の度にのしかかかっているのではないでしょうか。
いきなり100点を目指すのは無謀です。60点のマニュアルをブラッシュアップしていくのです。
一度踏ん張って60点のマニュアルを作ってみてください。それだけでも教育コストの削減をはじめ、経営方針のブレークダウンやオペレーションの棚卸によるムダ・ムラ・ムリの発見といった大きなメリットを得られるはずです。
まとめ
先述の通り、実用性の高いマニュアルはメリットが大きい反面、一時的に相応の手間と労力を必要とします。
ただし、いつまでも場当たり的な教育やスタッフ個々の受動的スキルアップに期待していては計画的な生産性向上、人件費の適正化を図ることはできません。一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか。
ご質問ご相談は以下のフォームにて承っております。また必要とあらばマニュアル作成のフォローや代行についてもご提案いたしますのでお気軽にお問い合わせください👦